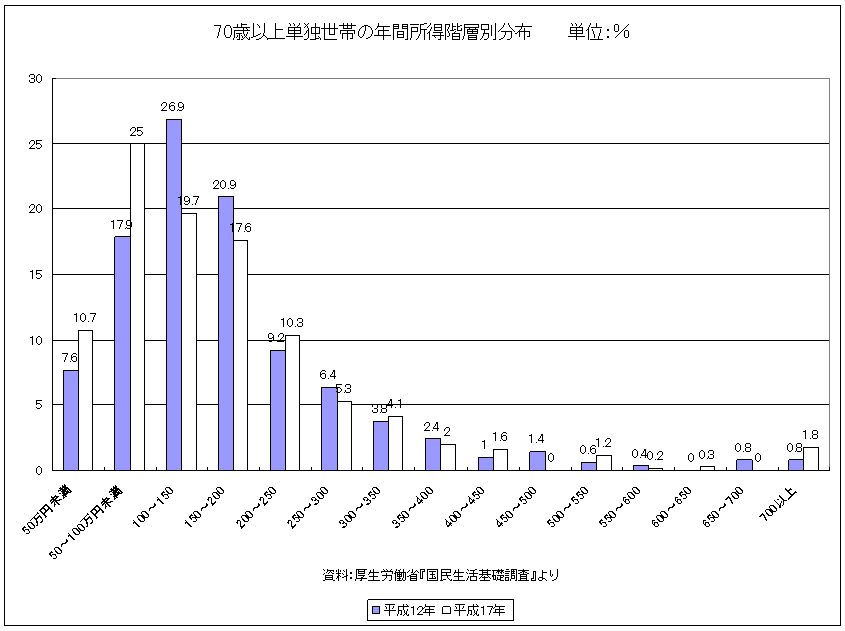
労働運動総合研究所
執筆・監修 金澤誠一
1.算定の対象となる世帯と地域
高齢単身世帯モデルとして、75歳女性を想定した。
居住地としては、首都圏の中でも東京都練馬区とした。
この世帯の生活を前提として、その実態調査の基礎の上に、以下で述べる算定方法によって、一つの理論値に到達したのである。
2.算定の目的と方法
(1)目的と意義
その目的は、最低賃金、生活保護、最低保障年金などの社会保障運動の基礎資料を求めることにある。
これまで、運動の要求の「目安」として生活保護基準を用いる場合が多かったが、老齢加算や母子加算の段階的削減から廃止、そしてまた、保護基準そのものの引き下げが図られようとしているとき、もはや既存の保護基準では、「目安」となることができなくなってきた。新しい要求の目標が必要となっている。
収入の高さが問題であることは言うまでもないが、それだけでは不十分であろう。その収入で「どのようなことができるのか」「どのような状態となりうるのか」といった「生活の質」が問われなければならない。
(2)最低生活=「人間らしい生活」の考え方
第1に、「適切な栄養をえているか」「雨露をしのぐことができるか」「避けられる病気にかかっていないか」「健康状態にあるか」といった基本的な健康・生命を維持するための「生活の質」(アマルティア・センの言う生活の「機能」、アマルティア・セン著、池本幸生・野上裕生・佐藤仁訳『不平等の再検討』岩波書店、1999年、参照)を確保すること。
第2に、「読み書きができるか」「移動することができるか」「人前に出て恥をかかないでいられるか」「自尊心を保つことができるか」「社会生活に参加しているか」といった社会・文化的な「生活の質」(アマルティア・センの言う生活の「機能」、前掲書参照)を確保すること。
こうした「生活の質」は憲法25条が規定する「健康で文化的な最低限度の生活」の意味内容であると考えた。
朝日訴訟の最高裁判決では、「健康で文化的な最低限度の生活」をその時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるものであると述べ、その概念は抽象的・相対的なものであるとしている。そしてその具体化に当たっては、国の財政事情を無視することができず、また多方面にわたる複雑多様な、しかも高度な専門的技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするとしている。
しかし、ここで述べた「生活の質」は、「健康で文化的な最低限度の生活」の意味内容について、一歩踏み込んだ解釈をするものである。相対的概念という意味で言えば、上記の「生活の質」を達成するためのさまざまな財やサービスが、時代とともに社会とともに変化するということである。しかし、上記の「生活の質」そのものは、歴史的にも社会的にも「絶対的」なものであると考える。
言うまでもなく、個々人が自分の価値や目的あるいは人生設計を選択し、それに向かって活動することは自由(「積極的自由」)である。その意味では価値や目的、生活は多様化するのである。そうした自分が選択した価値や目的あるいは人生設計が、その人の人格を形成することになる。しかし、そうした人格は、それを取り巻く社会的・経済的あるいは文化的環境によって、影響を受けることが多いのである。低所得層や貧困層は、長い人生の中でさまざまな大切なものを失いながら生きていく場合が多いであろう。その悲哀ははかりしれないものがある。また、個々人が置かれている貧困や差別や身体的・精神的状態の違いによって、自分自身の欲求・価値・目的を抑制する可能性も高いのである。価値の多様性よりは、こうした個々人が置かれている身体的・精神的状況の多様性や、貧困や差別などの社会的状況の多様性に配慮する必要があるのである。そうした人格を取り巻く環境・状況の改善なくして、個々人の自由は保障されないと考えるのである。言い換えるならば、貧困からの自由としての最低生活の保障、差別からの自由、身体的・精神的状況からの自由といった「消極的自由」(「何々からの自由」として「何々からの開放」を意味している)が、公共政策によって実現されてこそ、積極的な自分自身の選択した価値や目的に向かって活動する自由が保障されるのである。
(3)算定の前提
最低生計費は、その前提となる人々が置かれている身体的・精神的状況や社会状況の違いへの社会的配慮(公共政策)によって異なる。本来、そうした公共政策をも合わせた総合的なナショナルミニマムが必要である。ここでは、ナショナルミニマムの体系の「要」として「最低生計費」を試算するのである。したがって、ここでは、現在の公共政策に基づく社会的諸制度を前提とした。それは、社会保障・社会福祉諸制度や、住宅・教育などの「生活基盤」や人権、平和の状態などを意味している。
(4)算定の方法
試算の方法としては、マーケットバスケット方式(全物量積み上げ方式)を採用した。それは、上記の目的を達成するために必要であるからである。最低限必要な「生活の質」を満たすために、どれだけの財が必要かを測るためには、必要な物量を一つ一つ積み上げる方法が最も適している。また、その当不当を判断するのに理解しやすいと考えた。それがこの方式を採用した最大の理由であるが、また、この方式の欠点も古くから指摘されている。それは、食費についてはカロリー計算や必要栄養を満たすような栄養学による一定の指標が存在するが、それ以外の費目については、具体的な指標が存在しない、といった指摘である。この欠点をどれだけ克服できるかが、この方式を採用して算定する場合、最大の鍵となる。
ここで算定した「最低生計費」は一種の理論的生計費ではあるが、最低生活をありうべき一定の理想として現実の生活から遊離させて考えているわけではない。今日の労働者世帯の生活様式、慣習、社会活動を把握するために、「持ち物財調査」や「生活実態調査」「価格調査」を実施し、それを基礎資料として算定しているところに特徴がある。その算定の基本的な方法は、以下の通りである。
(注)マーケットバスケット方式で算定した例として、1974年に当時の総評が算定した「理論生計費」がある。これは、労働者の「あるべき生活像」を想定して算定している点に特徴がある。例えば、「より人間らしい生活」として次のように想定している。「労働時間短縮等を反映した能動型、主体的行動型の余暇を考慮すべきだ」として、「ハイキング、スキー、登山、家族旅行などの比重を高めたほか、単身世帯では語学研修、複数世帯では主婦のけいこごと、夫の趣味(釣り)、長男のサイクリング、長女のピアノのレッスンなどを配慮することにした。」と述べている。その結果、算定された「理論生計費」は、現実の賃金とは大きくかけ離れたものとなった。この例は、労働者の現実の生活様式や社会慣習、社会活動から遊離して理論的に生計費を算定したものといえる。
① 家具・家事用品、被服及び履物、教養娯楽耐久財、書籍・他の印刷物、教養娯楽用品、理美容用品、身の回り用品などは、「持ち物財調査」に基づいて、原則7割以上の保有率の物を「人前にでて恥をかかないでいられる」ために最低限必要な必需品と考え、それぞれの費目毎に積み上げて算定した。また、耐用年数については、国税庁「減価償却資産の耐用年数等に関する政令」を参考にした。
購入先について、生活実態調査に基づき想定した。下着については、最も多いのが「大型スーパー」で46.7%、次いで「近くの商店街」の23.3%、「百貨店」の16.7%と続いていた。下着の購入先として最も多い大型スーパーを想定した。
洋服については、最も多いのが「近くの商店街」で26.7%、次いで「百貨店」の20.0%、「専門店」の16.7%、「大型スーパー」の13.3%、「生協」の10.0%であった。ばらつきが激しく、特定することが困難であるが、比較的安く品数のそろっている「大型スーパー」を想定した。
電化製品については、同様に、最も多いのが「大型電気店」で43.3%、次いで「近くの電気屋さん」の33.3%、「大型スーパー」の20.0%であった。このことから最も多い「大型電気店」を想定した。
家庭雑貨については、最も多いのが「大型スーパー」で53.3%、次いで「近くの商店街」の26.7%、「百円ショップ」の10.0%と続いていた。この結果から最も多い「大型スーパー」を想定した。
「価格調査」の方法としては、それぞれの品目のそのお店の最低価格、最多・標準価格、最高価格を調査した。外出用の品目については、「人前に出て恥をかかないように」最低価格は避けて、標準価格を用いた。それ以外については、最低価格を用いている。
② 食費については、2005年の総務庁「家計調査」の品目分類に基づいて、最も年間収入の低い第1五分位階層の100g当たりの消費単価を4つの食品群に分けてそれぞれ計算した。なお、2008年5月時点での食費の物価上昇率は、2005年に比べ2.6%増となっていることを考慮し、食費合計額に物価上昇分を加えている。
次に、女子栄養大学出版部『2008年版五訂増補食品成分表資料編』に基づき、世帯モデル毎に、1日当たりの必要なカロリーを算出した。
また、「4つの食品群の年齢別・性別・身体活動レベル別食品構成(1人1日当たりの重量=g)」(香川芳子:女子栄養大学教授案)に基づいて必要な栄養を満たすように、食費を試算した。香川教授の試案に基づきエネルギー必要量の1割は嗜好品でまかなうようにした。ただし、高齢者の嗜好を考慮して、嗜好品の割合を1割から2割に増やし、生鮮野菜や果物、助貝類を積極的に摂取してもらうことにした。また、嗜好品の単価を少し高めにとっている。なお、食べ残しなどの廃棄率を5%とした。
すでに現役を離れて年金生活をしていることを想定していることから、朝食、昼食、夕食は、家で食べることにした。
また、仕事の帰りや休日にお酒や会食にいきますかという問に対し、最も多いのが「月の数回程度」の40.0%、「ほとんでない」の23.3%、「週に2〜3回」の16.7%と続いていた。この結果から、友人などとの会食を月4回とした。その費用については、2000円台が最も多く35.0%、次いで1000円台と3000円台の15.0%、4000円台の10.0%と続いていた。1000円台から4000円台に集中しているのが分かるが、最低費用に近い1回2,000円とした。
③ 住居費については、公営住宅は少なく、現実に入ることが困難なため、民間借家を想定した。居住面積については、国土交通省「住生活基本計画」(平成18年度から平成27年度)による「最低居住面積水準」に基づき、単身世帯25m2、2人世帯30m2、3人世帯40m2、4人世帯50m2とした。
住宅情報誌による賃貸アパート・マンションの家賃を、東武東上線沿線(朝霞台まで)で調査した結果、23m2〜25m2で最低価格5.0万円、最高価格8.0万円であった。平均すると6.5万円となる。ここでは、最低価格の5.0万円を想定した。
また、生活実態調査では、更新期間は、2年ごとが4割、1年ごとが2割、なしが1割存在した。この結果から、2年ごとの更新を想定した。同調査では更新料はほぼ1ヶ月分の家賃であると想定できた。
④ 教育費については、文科省平成18年度「子どもの学習費調査」に基づいて算定した。学校給食費は、食費の中に入れるために除外した。この調査の結果に基づき、支出率7割以上の費目について、その支出平均額を計上した。ただし、老齢単身の場合には、教育費は該当しない。
⑤ 教養娯楽サービスについては、「生活実態調査」では、日帰り旅行については、「なし」が80.0%に上り、月1回〜2回が10.0%という結果から、日帰り旅行はないものとした。一泊以上の旅行については、「なし」が33.3%、年1回〜3回が合計46.7%、4回以上の合計が16.6%という結果から、年2回と想定した。また、1回の費用としては、最も多いのが「1万〜2万5千円」と「2万5千〜5万円」のそれぞれ36.8%、次いで「5万〜7万5千円」の15.8%と続いている。この結果から、1回3万円を想定した。また、休日や余暇の過ごし方について(複数回答)は、最も多いのが「自宅で休養」の60.0%であるが、「読書」23.3%、「映画などの鑑賞」の20.0%、「園芸・野菜づくり」の10%、「その他の趣味」の23.3%というふうに、休日や余暇として、趣味を多彩に持っていることがうかがえる。映画・観劇、スポーツなどの鑑賞などを月1回するものと想定し、その費用として1回2,000円とした。
⑥ 理美容サービス
理髪料として、成人男性の場合、1回4,000円、中学男子 1回3,000円、小学女子 1回2,500円、ヘアーカット代 1回3,300円として計算した。2か月に1回利用とした。
⑦ 交通・通信費については、「生活実態調査」では、自動車があるかに対し、「ない」と答えた人の割合が圧倒的に多く86.7%に上っていた。また、その必要性については、「なければないでよい」の73.3%であり、「生活必需品」と答えた人は3.3%でしかなかった。首都圏であり、公共交通機関が比較的利用しやすいことを前提に、自動車の所有はないものと想定した。自転車についても、「持ち物財調査」でもその保有は56.5%でしかなく、自転車もまたないものとした。
買い物や行楽の時は、公共交通機関の利用を想定した。その際の交通費として1回500円とし、月6回とした。
通信費については、「平成16年全国消費実態調査」より70歳以上単身世帯女性の月平均額を用いた。
⑧ 水道・光熱費、医療費については、「平成16年全国消費実態調査」より70歳以上単身世帯女性の月平均額を用いた。
⑨ 交際費・その他については、生活実態調査の結果をみると、第1に、親戚などの結婚式・お葬式などに参加しているかとの問に対し、最も多いのが「ほとんど参加」」の60.0%、次いで「他の費目を節約して参加」「経済的に無理」「最近ほとんどよばれない」がそれぞれ13.3であった。「参加しないことにしている」と答えた人はいなかった。その回数は、最も多いのが年2回で40.9%、次いで3回の22.7%、5回以上の18.2%、1回と4回が9.1と続いていた。2回が最も多いが、3回から5回以上を合計すると50.0%となることを考慮して、年3回の結婚式やお葬式・法事などへの参加を想定した。その費用は交通費や貸衣装代、着付け代、髪セット代などを含め、1回3万円とした。言うまでもなく、これらを総計すると1回3万円では不足する可能性が高い。しかし、年3回の内1回程度は3万円を超えるとしても後の2回3万円に満たないとして、平均すると1回3万円と想定した。
第2に、お中元やお歳暮を贈っているか、という問に対しては、最も多いのが「贈らないことにしている」で43.3%、次いで「毎年決まって贈っている」の33.3%、「無理して贈っている」と「経済的に無理」がそれぞれ6.7%、「贈ってくれる人だけに」が3.3%と続いている。この結果からみると、「贈らないことにしている」と無理してか決まってかに関わらずとにかく贈っている人の割合は43.3%と同率となった。「経済的に無理」が6.7%を考慮すると、贈る意志のある人がやや多いということになる。その軒数についても聞いているが、最も多いのが5軒の30.8%、次いで3軒の15.4%であった。また、6軒以上の合計は30.8%に上っていた。また、その金額についても聞いている。その結果によれば、2,000円台と5,000円台にそれぞれ30.8%分布していた。それ以外では4,000円台が15.4%となっていた。こうした結果を踏まえて、普段お世話になり、さまざまな贈りものをいただいている人へのお返しとしてお中元やお歳暮は贈ることを想定し、その軒数はお中元とお歳暮をそれぞれ3軒ずつ計6軒とした。またその金額は1軒送料込みで3,000円とした。
第3に、お見舞金やせん別、お年玉などについては、最も多い回答は「機会があればあげている」の53.3%で、次いで「無理してあげている」の23.3%、「経済的に余裕がない」「最近あげる機会がない」「あげないことにしている」はそれぞれ6.7%であった。この結果から、お見舞金やせん別、お年玉などの贈り物は、年6回あげることを想定し、その費用は1回5,000円とした。
第4に、自治会費などの負担費として、年間7,800円とした。自治会費の他に社会福祉協議会会費や赤い羽根の寄付、お祭りの寄付などを想定した。
第5に、住宅関係費として、共益費は、賃貸住宅情報誌による調査では、共益費の平均が約3,000円であった。
第6に、子どもやお孫さんが訪ねてきた場合の接待費として、年3回、1回の費用として5,000円を想定した。
第7に、学生時代の同窓会を年1回、8,000円の参加費として算定した。
第8に、老人クラブなどの会費として、年間3,000円を想定している。
第9に、その他・信仰費として、お彼岸やお盆に際してのお墓参りを年3回想定した。お花代、お線香代、ロウソク代、お布施、行き帰りの交通費などを含め1回5,000円とした。
⑩ こづかいについては、これまでの算定では計上しなかった教養娯楽費としての切り花代、鉢植え代などや旅行時の使い捨てカメラやその現像代など、また、飲食費としての喫茶店でのコーヒー代などを、こづかいとして一括してここに計上した。これは、「持ち物財調査」では保有率が分散していて7割には満たないが、個々人の趣味などの価値観の多様性を考慮したものである。その額は、1日200円として月6,000円とした。
⑪ その他、予備費として、消費支出の1割を計上している。これは、これまで計上してきた最低生計費は、いわば平均的な人間を想定したものである。しかし、実際には、個々人の身体的・精神的特徴の多様性が存在し、例えば、身長や体重の違いにより熱エネルギー量は異なる。また、めがねを必要としたり補聴器を必要としたり、歩行困難なため交通通信費も異なる可能性がある。その人の健康状態によっても異なるのである。また、個々人が置かれている社会状況の違いにも考慮する必要がある。例えば、個々人の交際の幅はその人の歩んできた人生によって異なり、それにともない冠婚葬祭費なども異なる可能性がある。そういった点を考慮して予備費を設けたのである。
II 高齢単身世帯の費目毎の最低生計費試算
上記の算定方法に基づいて、以下では費目毎に算定した。なお、算定に当たっては、小数点以下は四捨五入している。
1.食費の算定
表1−1.4つの食品群別にみた、100g当たりの消費単価
| 第1群 | 第2群 | ||||
| 乳・乳製品 | 卵 | 魚介・肉 | 豆・豆製品 | ||
| 26.60円 | 22.11円 | 129.41円 | 54.08円 | ||
| 第3群 | 第4群 | ||||
| 野菜・海草 | いも類 | 果物 | 穀類 | 砂糖 | 油脂 |
| 42.57円 | 24.33円 | 37.13円 | 45.48円 | 17.45円 | 34.28円 |
| 嗜好品(菓子、飲料、酒類) | |||||
| 57.13円(100カロリー当り68.23円) | |||||
「高齢単身世帯モデル」
75歳女性 1日当たり1,550kカロリー
表1.75歳、女性、身体活動レベルII、4つの栄養群別、必要な食品構成と金額
| 第1群 | 第2群 | ||||||
| 乳・乳製品 | 卵 | 魚介・肉 | 豆・豆製品 | ||||
| 必要量 | 金額 | 必要量 | 金額 | 必要量 | 金額 | 必要量 | 金額 |
| 250g | 66.5円 | 50g | 11.1円 | 100g | 129.4円 | 80g | 43.3円 |
| 第3群 | |||||||
| 野菜・海草 | いも類 | 果物 | |||||
| 必要量 | 金額 | 必要量 | 金額 | 必要量 | 金額 | ||
| 350g | 149円 | 100g | 24.3円 | 200g | 74.3円 | ||
| 第4群 | |||||||
| 穀類 | 砂糖 | 油脂 | |||||
| 必要量 | 金額 | 必要量 | 金額 | 必要量 | 金額 | ||
| 180g | 81.9円 | 5g | 0.9円 | 10g | 3.4円 |
1日エネルギー必要量の90%とその他の栄養必要量を満たし、それに嗜好品を加えた金額は、
| 1,395kカロリー | 584.1円 |
| 嗜好品・155kカロリー | 105.8円 |
| 合計 | 689.9円 |
ただし、高齢者の嗜好を考慮して嗜好品の割合を1割から2割に修正した。また、嗜好品の単価をやや高めにとると、以下のようになる。
| 1,240kカロリー | 519.2円 |
| 嗜好品・310kカロリー | 217.0円 |
| 合計 | 736.2円 |
従って、1ヶ月、すべて家で食事をする場合には、736.2円*30日=22,086円となる。
友人などとの会食は、次の通り算定した。
会食 1回 定食(刺身膳)とお酒1本
489kカロリー+200kカロリー=689kカロリー
月4回 2,756kカロリー 8,000円
従って、家での食事、会食の内訳は次のようになる。
| 家での食事 | 43,744kカロリー | 20,777円 | ×1.026=21,317円 |
| 会食 | 2,756kカロリー | 8,000円 | |
| 廃棄率(5%) | 2,325kカロリー | 1,133円 | |
| 合計 | 48,825kカロリー | 30,450円 | |
2.住居費の算定
「高齢単身世帯モデル」
| 合計 | 52,083円 | |
| 家賃 | 月 | 50,000円 |
| 更新料 | 月当たり | 2,083円 |
3.水道・光熱費の算定
「高齢単身世帯モデル」
| 合計 | 10,364円 |
| 電気代 | 4,711円 |
| ガス代 | 2,696円 |
| 他の光熱 | 708円 |
| 上下水道代 | 2,249円 |
4.家具・家事用品の算定
「高齢単身世帯モデル」
| 合計 | 5,864円 |
a.家庭用耐久消費財 月額 2,088円
家事用耐久財
| 品目 | 価格 | 耐用年数 | 消費量 | 月価格 | 備考 |
| 自動炊飯器 電気冷蔵庫 電気掃除機 電気洗濯機 電子レンジ ガステーブル 電気アイロン |
4,970 18,700 7,970 18,700 9,700 12,700 3,480 |
6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 |
1 1 1 1 1 1 1 |
69 260 136 260 135 176 48 |
3合炊 99リットル 4.2kg |
| 小計 | 1,084 |
冷暖房用機器
| 品目 | 価格 | 耐用年数 | 消費量 | 月価格 | 備考 |
| ルームエアコン 電気こたつ 扇風機 |
49,700 8,000 2,980 |
6年 6年 6年 |
1 1 1 |
690 111 41 |
6畳用 |
| 小計 | 842 |
一般家具
| 品目 | 価格 | 耐用年数 | 消費量 | 月価格 | 備考 |
| 整理ダンス スチール棚 食卓用テーブル |
19,700 4,970 4,470 |
15年 15年 15年 |
1 1 1 |
109 28 25 |
|
| 小計 | 162 |
b.室内装備品 月額 269円
| 品目 | 価格 | 耐用年数 | 消費量 | 月価格 | 備考 |
| 掛け時計 目覚まし時計 照明器具 カーテン こたつ布団・カバー |
7,350 2,100 5,970 1,470 4,980 |
8年 8年 8年 5年 5年 |
1 1 1 1 1 |
77 22 62 25 83 |
1.0m×2.0m |
| 小計 | 269 |
c.寝具類 月額 874円
| 品目 | 価格 | 耐用年数 | 消費量 | 月価格 | 備考 |
| 敷きふとん 掛けふとん タオルケット 毛布 まくら シーツ ふとんカバー まくらカバー |
4,970 3,970 797 2,970 797 797 1,290 497 |
5年 5年 3年 3年 3年 2年 2年 2年 |
2 2 2 2 2 3 3 3 |
166 132 44 165 44 100 161 62 |
|
| 小計 | 874 |
d.家事雑貨 月額 1,289円
| 品目 | 価格 | 耐用年数 | 消費量 | 月価格 | 備考 |
| 飯茶碗 湯飲み茶碗 コーヒー・紅茶茶碗 どんぶり 吸い物茶碗 盛り皿・盛り鉢 スープ皿 果物用ガラス皿 中皿 小皿 中ばち 小ばち コップ スプーン フォーク ナイフ 水筒 茶筒 急須 砂糖入れ しょうゆ差し 弁当箱 タッパー お盆 大鍋 中鍋 小鍋 フライパン 中華鍋 やかん 米びつ 洗いおけ 水切りざる・かご ボール 包丁 まな板 すり鉢・すりこぎ たわし・スポンジ おろし器 ふきん掛け はし しゃもじ ふきん フライ返し あわたて器 干し物さお くずかご 座敷ほうき 洗濯用バケツ・かご タオル バスタオル 電球 蛍光灯 スパナ ドライバー 金づち ペンチ 玄関用マット 懐中電灯 洗面器 |
97 95 197 197 97 297 890 300 480 380 300 200 97 98 98 98 2,580 690 397 451 490 880 500 1,029 1,980 1,180 1,180 980 1,680 777 880 1,780 197 227 997 970 780 97 680 398 97 197 197 500 400 598 497 1,280 480 197 597 136 577 1,260 97 609 1,597 780 260 600 |
2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 1年 5年 5年 5年 5年 1年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 1年 1年 1年 2年 15年 15年 15年 15年 5年 5年 5年 |
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
8 8 16 16 8 25 74 25 40 32 25 17 8 3 3 3 43 12 7 8 8 15 42 17 33 20 20 16 28 13 15 30 3 8 17 16 13 8 11 7 8 3 82 8 7 10 8 21 8 82 249 11 24 7 1 3 9 13 4 10 |
2本、30w |
| 小計 | 1,289 |
e.家庭用消耗品 月額 1,344円
| 品目 | 価格 | 耐用年数 | 消費量 | 月価格 | 備考 |
| ポリ袋 ラップ ティッシュペーパー トイレットペーパー 台所用洗剤 トイレ用洗剤 住宅用洗剤 洗濯用洗剤 漂白剤 |
127 108 268 349 127 177 176 257 398 |
1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 |
120 12 18 68 12 12 5 12 10 |
25 108 80 165 127 177 73 257 332 |
50枚 5個 12ロール |
| 小計 | 1,344 |
6.被服および履物の算定
「高齢単身世帯モデル」
| 被服 | 6,407円 |
| 履物 | 790円 |
| 洗濯代 | 350円 |
| 合計 | 7,547円 |
洋服
| 品目 | 価格 | 耐用年数 | 消費量 | 月価格 | 備考 |
| アンサンブル 礼服 オーバーコート ジャケット スカート スラックス ジャンパー |
15,800 34,650 10,500 10,500 2,990 3,990 2,900 |
4年 8年 5年 5年 3年 3年 4年 |
2 1 1 3 5 5 2 |
658 361 175 525 415 554 121 |
|
| 小計 | 2,809 |
シャツ・セーター類
| 品目 | 価格 | 耐用年数 | 消費量 | 月価格 | 備考 |
| ブラウス Tシャツ・ポロシャツ 長袖・半袖シャツ セーター・カーディガン |
1,990 1,500 2,990 1,990 |
2年 2年 2年 3年 |
3 5 5 3 |
249 313 623 166 |
|
| 小計 | 1,351 |
下着
| 品目 | 価格 | 耐用年数 | 消費量 | 月価格 | 備考 |
| パンティ ブラジャー シャツ(肌着) パジャマ |
300 900 300 1,900 |
1年 1年 1年 2年 |
10 2 5 2 |
250 150 125 158 |
|
| 小計 | 683 |
他の被服
| 品目 | 価格 | 耐用年数 | 消費量 | 月価格 | 備考 |
| パンティストッキング ソックス スカーフ 手袋 ベルト エプロン |
980 1,000 1,300 700 1,995 1,000 |
1年 1年 5年 2年 5年 1年 |
5 10 3 2 1 2 |
408 833 65 58 33 167 |
|
| 小計 | 1,564 |
履物
| 品目 | 価格 | 耐用年数 | 消費量 | 月価格 | 備考 |
| 靴・ブーツ 運動靴・スニーカー サンダル スリッパ |
5,000 2,950 1,900 580 |
2年 2年 2年 1年 |
2 2 1 1 |
417 246 79 48 |
|
| 小計 | 790 |
洗濯代
アンサンブルとオーバーコート計3着分を想定した。
1着1,400円*3/12=月額 350円
7.保健医療費の算定
「高齢単身世帯モデル」
| 合計 | 8,139円 |
| 医薬品 | 1,429円 |
| 健康保持用摂取品 | 1,288円 |
| 保健医療用品・器具 | 1,020円 |
| 保健医療サービス | 4,402円 |
8.交通・通信費の算定
「高齢単身世帯モデル」
| 合計 | 7,970円 |
| 交通 | 3,000円 |
| 通信 | 4,970円 |
9.教養娯楽費の算定
「高齢単身世帯モデル」
| 合計 | 12,589円 |
a.娯楽用耐久財
| 品目 | 価格 | 耐用年数 | 消費量 | 月価格 | 備考 |
| カラーテレビ ラジカセ |
59,700 3,980 |
5年 5年 |
1 1 |
995 66 |
20インチ |
| 小計 | 1,061 |
b.書籍・他の印刷物
| 品目 | 価格 | 耐用年数 | 消費量 | 月価格 | 備考 |
| 日刊新聞 単行本 |
3,850 1,000 |
月1紙 月1冊 |
3,850 1,000 |
||
| 小計 | 4,850 |
c.教養娯楽サービス
| 品目 | 価格 | 耐用年数 | 消費量 | 月価格 | 備考 |
| 帰省・旅行 レジャー・スポーツ NHK受信料 |
20,000 2,000 1,345 |
年2回 月1回 |
3,333 2,000 1,345 |
||
| 小計 | 6,678 |
10.理美容費の算定
「高齢単身世帯モデル」
| 合計 | 4,590円 |
a.理美容用品 2,940円
| 品目 | 価格 | 耐用年数 | 消費量 | 月価格 | 備考 |
| ヘアードライヤー 歯ブラシ ヘアブラシ かみそり 化粧石鹸 シャンプー ヘアリンス 歯磨き 化粧水 乳液 ファンディーション 口紅 |
980 98 525 75 197 298 228 117 448 448 1,050 1,050 |
6年 1年 3年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 |
1 3 1 12 12 12 12 12 12 8 12 2 |
14 24 15 75 197 298 228 117 448 299 1,050 175 |
3個 |
| 小計 | 2,940 |
b.理美容サービス 月 1,650円
12.身の回り用品の算定
「高齢単身世帯モデル」
身の回り用品 合計 827円
| 品目 | 価格 | 耐用年数 | 消費量 | 月価格 | 備考 |
| 傘 旅行用カバン ショルダーバック ハンドバック ショッピングバック リュックサック 財布 腕時計 指輪 ブローチ 帽子 ハンカチ |
997 2,795 4,000 4,095 1,900 1,200 1,000 5,230 6,090 2,940 2,390 535 |
2年 5年 5年 5年 5年 5年 2年 10年 15年 15年 5年 1年 |
2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 |
83 47 67 68 32 20 41 44 34 49 119 223 |
|
| 小計 | 827 |
13.交際費・その他の算定
「高齢単身世帯モデル」
交際費・その他 月額 18,567円
| 品目 | 価格 | 耐用年数 | 消費量 | 月価格 | 備考 |
| 冠婚葬祭贈与金 お中元・お歳暮贈与金 見舞金・お年玉など贈与金 住宅関係負担費 自治会費等 接待費 同窓会参加費 老人クラブなどの会費 お寺参り |
30,000 3,000 5,000 3,000 7,800 5,000 8,000 3,000 5,000 |
年3回 年6軒 年6軒 月 年 年3回 年1回 年 年3回 |
7,500 1,500 2,500 3,000 650 1,250 667 250 1,250 |
||
| 小計 | 18,567 |
14.こづかいの算定
「高齢単身世帯モデル」
月 6,000円
III 最低生計費 総括表
| 高齢単身世帯 | |
| 75歳女性 | |
| 賃貸アパート 1K25m2 | |
| 消費支出 | 164,990 |
| 生活扶助相当額 | 105,731 |
| 生活扶助額・加算含まず | 75,920 |
| 生活扶助額・加算含む | 93,850 |
| 食費 | 30,450 |
|
家での食費 外食・会食 廃棄率5%を加算 |
21,317 8,000 1,133 |
| 住居費 | 52,083 |
|
家賃 更新料月当たり |
50,000 2,083 |
| 光熱・水道 | 10,364 |
|
電気代 ガス代 他の光熱 上下水道 |
4,711 2,696 708 2,249 |
| 家具・家事用品 | 5,864 |
|
家庭用耐久財 室内装備・装飾品 寝具類 家事雑貨 家事消耗品 |
2,088 269 874 1,289 1,344 |
| 被服及び履き物 | 7,547 |
|
被服費 履物 洗濯代 |
6,407 790 350 |
| 保健医療 | 8,139 |
|
医薬品 健康保持用摂取品 保健医療用品・器具 保健医療サービス |
1,429 1,288 1,020 4,402 |
| 交通・通信 | 7,970 |
|
交通費 通信費 |
3,000 4,970 |
| 教育 | − |
|
学校教育費 学校外教育費 |
|
| 教養娯楽 | 12,589 |
|
教養娯楽用耐久財 書籍・他の印刷物 教養娯楽サービス 旅行・帰省 レジャー・スポーツ NHK受信料 |
1,061 4,850 6,678 3,333 2,000 1,345 |
| その他 | 29,984 |
|
理美容用品 理美容サービス 身の回り用品 こづかい 交際費・その他 |
2,940 1,650 827 6,000 18,567 |
| 非消費支出 | 25,199 |
|
所得税 住民税 社会保険料 |
2,476 9,241 13,482 |
| 予備費 | 16,000 |
|
最低生計費(税抜き) (税込み)月額 (税込み)年額 |
180,990 206,189 2,474,268 |
IV 算定された最低生計費の位置
1. 生活保護基準との比較
(1)高齢単身世帯の生活保護基準
東京都のような大都会は、「1級地−1」とランクされ、基準額は最も高くなる。まず、日常生活費として算定される個人単位の「生活扶助費」として、「第1類」がある。その額は、年齢階層別に定められ、70歳以上は月額32,340円である。日常生活費の中の世帯単位消費される部分は「第2類」とされ、その額は世帯人員毎に定められ、単身者の場合には月額43,430円である。従って、生活扶助額の合計は、第1類と第2類を合わせた額となり、75,770円である。
その他、当該モデルのように賃貸アパートに住んでいる場合には、「住宅扶助」が支給される。その「一般基準」は月額13,000円としているが、大都会のようにこのような低額のアパートは存在しないため、「特別基準」が定められている。東京都の場合、特別基準は単身世帯で53,700円以内となっている。当該モデルのほぼ家賃に近似している。また、暖房費として冬季加算(11月から3月まで)が東京都の場合には月3,090円が支給される。その他、期末一時扶助費(12月)として14,180円の支給がある。冬季加算と期末一時扶助費を月に直すと、2,469円となる。
従って、生活扶助額と住宅扶助額、冬季加算、期末一時扶助費を合計すると、月130,322円ということになる。これに廃止された老齢加算額17,930円と加えると148,252円となる。言うまでもなく、この額には税金や保険料が含まれていない。生活保護受給者はそれらが免除されている。また、病気などで医療費がかかる場合には、別途医療扶助が現物で支給される。
(2)生活保護基準と算定された「最低生計費」との比較
上記の老齢単身世帯モデルの生活保護制度による保護基準とここで算定された「最低生計費」とを比較することにするが、その場合、生活保護受給世帯の場合には免除されている税金や保険料、NHK受信料や医療扶助相当額を「最低生計費」から差し引いた額で比較するのが妥当であろう。
当該モデルの生活保護制度による保護基準130,322円、老齢加算を加えると148,252円であるから、算定された「最低生計費」の保護基準相当額157,814円と比較すると、老齢加算を含まない保護基準額を100とすれば120.1、老齢加算を含めた保護基準額を100とすれば106.4ときわめて近似しているのが分かる。
2.「最低生計費」未満の人々の割合
では、算定された「最低生計費」に満たない人々の割合はどれくらい存在するのであろうか。
次の図は、厚生労働省「国民生活基礎調査」により、70歳以上単独世帯の年間所得階層別にみた所得階層別分布を平成12年と平成17年とで比較したものである。これをみると、平成12年には最頻度値が100〜150万円未満であるのに対し、平成17年には50〜100万円未満へと所得分布が一ランク低下しているのが分かる。それだけ、100万円未満層が増加し、100〜200万円未満層が低下していることを示している。
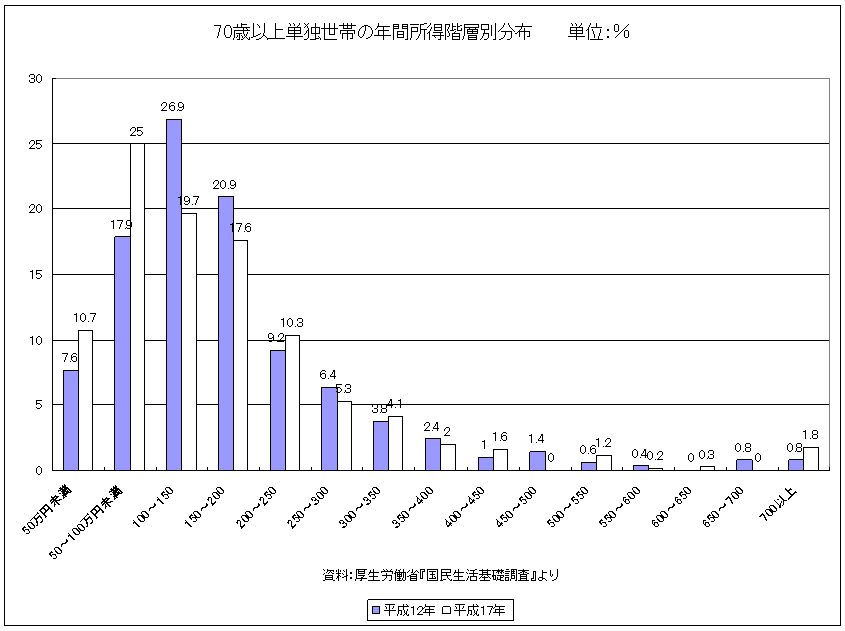
では、算定した「最低生計費」年間247万円未満の割合は、どれくらいになるのであろうか。平成12年には250万未満層の累計82.5%、平成17年では83.5%存在している。
仮に、先に見た生活保護制度における最低生活費=生活保護基準としてみたらどうであろうか。また、算定された「最低生計費」の生活保護相当額でみたらどうであろうか。生活保護基準は老齢加算を含むと年額1,779,024円、約178万である。老齢加算を含まないと1,563,864円、約156万円である。他方、「最低生計費」には税金や保険料の徴収が免除され、医療扶助相当額も免除され、NHK受信料も免除されるものとして「最低生計費」の保護基準相当額を計算すると1,893,768円、約189万円となる。
平成17年でみると、老齢加算を含む保護基準未満は46.7%、老齢加算を含まない保護基準未満は38.1%ということになる。他方、「最低生計費」の保護基準相当額未満は57.5%となる。