
2000擭俆寧侾擔乮捠姫122崋乯

2000擭俆寧侾擔乮捠姫122崋乯
栚丂丂丂師 姫摢尵 丂娫嬤偵尒傞庒偄楯摥幰偺棏偨偪乧乧乧忋戨丂恀惗
榑丂暥 丂乽IT妚柦乿偵偮偄偰峫偊傞乧乧乧乧乧乧撊旜丂丂撜
丂嵟嬤姶偢傞偙偲乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧乧捤揷丂媊旻
丂係寧偺尋媶妶摦傎偐
娫嬤偵尒傞庒偄楯摥幰偺棏偨偪
忋戨丂恀惗
丂弔偼丄戝妛傪嫀傞幰偲戝妛偵擖傞幰偲偑岎嶖偡傞婫愡偩丅偄傠偄傠側巚偄偑嫀棃偡傞丅偲傝傢偗嵟嬤偼丄妛惗丒懖嬈惗偲偺愙怗傪偮偆偠偰丄庒擭幐嬈棪偺崅傑傝傗庒擭楯摥椡偺棳摦壔傪敡偱姶偠偰丄峫偊崬傓丅
丂巹偺偮偲傔偰偄傞戝妛丒妛晹偱巹偺僛儈僫乕儖偵強懏偡傞傛偆側妛惗偼丄側傫傜偐偺堄枴偱乽堩扙幰乿偩丅偟偐偟丄斵傜傕幚幮夛偵弌偰怘傢側偗傟偽側傜側偄偲偄偆尰幚偵捈柺偡傞丅偲偙傠偑丄偦偆偄偆乽堩扙幰乿偨偪偑廇怑偡傞婡夛偼丄偙偺偲偙傠丄偲傒偵嫴傑偭偰偄傞丅偲偔偵彈巕妛惗偺偽偁偄丄怺崗偩丅崱擭俁寧偵懖嬈偟偨僛儈強懏妛惗20恖偺偆偪俇恖偼丄惓婯屬梡偺廇怑愭偑寛傑傜側偐偭偨丅偦傟偧傟偺屄恖偼丄岞柋堳帋尡傪庴尡偡傞幰丄帒奿帋尡偺庴尡傪婓朷偡傞幰丄傾儖僶僀僩偱摉柺偺惗妶傪堐帩偡傞幰側偳丄懡條偱偼偁傞丅偟偐偟丄偦偺婎慴偵偼屬梡忣惃偺埆壔偲戝懖楯摥幰偺楯摥忦審偺埆壔偑偁傝丄斵傜偼偦偺媞娤揑尰幚偵懳偟偰偦傟偧傟側傝偺寛抐傪偟偰戝妛傪屻偵偟偰偄偔丅
丂傑偨丄廇怑偡傟偽埨掕偟偨惗妶偵側傞偐偲偄偊偽丄偦偆偱偼側偄丅廇怑偟偰偄偭偨懖嬈惗偺偐側傝偺晹暘偑丄斾妑揑抁婜娫偺偆偪偵棧怑丒揮怑偡傞丅嶐擭俁寧偵懖嬈偟偨僛儈強懏妛惗偺偆偪丄巹偺抦傞尷傝丄偡偱偵俁恖偑嵟弶偺廇怑愭傪戅怑偟偨丅梌偊傜傟偨扨挷側巇帠偵懴偊傜傟側偔側傞幰丄尩偟偄楯摥偱恎懱傪偙傢偡幰側偳丅偦偺巔偼丄崅搙惉挿婜偵廤抍廇怑偟偨庒擭楯摥幰偺堦掕悢偑岺応傪敳偗弌偡偝傑傪巚偄偍偙偝偣傞丅摨偠偙偲偑丄尰嵼丄僒乕價僗嶻嬈偺偡偦栰偺戝懖楯摥幰偱婲偙偭偰偄傞偺偩偲巚偆丅
丂偙偆偄偆忬嫷偵偮偄偰丄楯摥徣側偳偼乽庒幰偺嬑楯娤偺懡條壔乿側偳偲偄偆尵梩偱寉乆偟偔偐偨偯偗傞偑丄幚懺偼偐側傝偺晹暘偑庒偄楯摥幰傪偲傝傑偔尩偟偄娐嫬偵婲場偟偰偄傞丅偨偩丄偙偺忬嫷偼儅僀僫僗偵偽偐傝昡壙偟偰偼偄偗側偄偲傕巚偆丅偙偆偟偨夁掱傪偮偆偠偰丄擔杮幮夛傪曪傒偙傫偱偄偨婇嬈庡媊偺庺敍偑夝偗傞偲傕巚偆偐傜偩丅
丂偟偐偟嫵巘偲偟偰偼丄斵傜偑楯摥幰偵側傞偵偁偨偭偰偳偺傛偆偵墖彆偟偰偄偗偽傛偄偺偐丅斀徣傪敆傜傟傞丅幚幮夛偵偼丄偨偨偐偆楯摥慻崌傪妀偲偡傞楯摥幰偺妶偒妶偒偲偟偨僱僢僩儚乕僋偑偁傞偺偩偲丄傕偭偲椡嫮偔岅傝偨偄偺偩偑乧丅
乮夛堳丒棳捠壢妛戝妛嫵庼乯
乽IT妚柦乿偵偮偄偰峫偊傞
撊旜丂丂撜
偼偠傔偵
丂21悽婭傪栚慜偵偟偨2000擭丅擭弶傔偐傜儅僗僐儈巻忋偱楢擔偺傛偆偵乽IT乿偲偐丄乽IT妚柦乿偲偐偄偭偨妶帤偑栚偵偮偔傛偆偵側傝丄偼偰側丠丄IT偲偼乽偄偭偨偄壗偐乿偲挷傋偼偠傔偨偺偑俀寧偺偼偠傔偱偟偨丅
丂乽IT乿偲偼丄塸岅偺僀儞僼僅儊乕僔儑儞丒僥僋僲儘僕乕乮忣曬媄弍乯偺棯徧偲偺偙偲偱偡偑丄偙傟偵乽妚柦乿偑偮偔偺偱傗傗偙偟偔側傝傑偡丅巇帠偑傜乽忣曬媄弍乿偵偮偄偰偼僴乕僪柺偱娭怱偑偁偭偨偺偱偡偑丄乽妚柦乿偵偮偄偰傕惌帯丒幮夛壢妛偺柺偱嫽枴偑偁傝傑偟偨丅婛懚拋彉偺曵夡傗尃椡峔憿偑媡揮偡傞偙偲傪乽妚柦乿偲偄偆奣擮偱嫵傢偭偰偒偨傛偆偵巚偄傑偡偑丄偙傟偑壗偱IT乮忣曬媄弍乯偲楢傜側偭偰乽IT妚柦乿側偺偐丅
丂婏偟偔傕嶐擭偺11寧丄帩偪姅夛幮偺傕偲偵暘妱乽嵞曇惉乿偟偨NTT偼揹榖偐傜忣曬棳捠夛幮偵揮姺偡傞偨傔丄俀枩侾愮恖偺恖堳嶍尭傪偼偠傔偲偟偨儕僗僩儔乽崌棟壔乿偱偁傞乽拞婜帠嬈寁夋乿傪敪昞偟傑偟偨丅偙傟傑偱偺愝旛嶻嬈偲偟偰偺揹婥捠怣帠嬈偐傜庤傪傂偒丄乽忣曬棳捠乿偲偄偆摼懱偺抦傟側偄帠嬈傪偍偙側偆偨傔丄恖丒暔丒僇僱偺偡傋偰偵傢偨偭偰嶍尭偡傞偲偄偄偩偟偨NTT偺摦岦傕IT妚柦偵娭學偑偁傞偺僇儌丄偲偄偆偙偲偱乽IT妚柦乿偵偮偄偰偺扵媶偵擬偑擖傝傑偟偨丅
IT偼宨婥夞暅偺愗傝嶥偐
丂乽IT娭楢偺愝旛搳帒奼戝丅悽奅嵟戝偺塼徎岺応丄壠揹梡儊儌儕乕憹嫮乿偲偄偭偨尒弌偟偑怴暦巻忋偱栚偵偲傑傝傑偟偨丅
丂乽僷僜僐儞傗実懷揹榖側偳偺廀梫奼戝偵懳墳偟偰丄塼徎傗揹巕晹昳側偳傪惗嶻偡傞揹婡丄慺嵽奺幮偑忣曬媄弍乮IT乯暘栰偺愝旛搳帒偺奼戝偵摦偒巒傔偨丅IT暘栰偺巗応奼戝偑丄嶻嬈奅偺搳帒傪偗傫堷偡傞峔恾偑慛柧偵側傝偮偮偁傞丅
丂愊嬌搳帒偺攚宨偵偁傞偺偼丄僷僜僐儞傗実懷揹榖偺岲挷偲丄BS僨僕僞儖曻憲偺杮曻憲奐巒傪擭枛偵峊偊偰亀崅夋幙丄懡僠儍儞僱儖丄憃曽岦宆亁偺僨僕僞儖僥儗價偺晛媦偑婜懸偝傟傞偨傔丅2000擭搙偺僷僜僐儞弌壸戜悢偼崱擭搙尒捠偟傛傝12亾懡偄1800枩戜偵払偟偦偆丅実懷揹榖傕壒惡偩偗偱側偔丄僀儞僞乕僱僢僩傪棙梡偟偨僨乕僞捠怣僒乕價僗偺奼廩偱壛擖幰偑憹偊偰偄傞丅乿乮侾寧14擔丒擔宱乯擭摢偵偁偨偭偰偲偄偆偙偲傕偁偭偨偺偱偟傚偆偐丄戝庤揹婡儊乕僇乕偺宱塩尒捠偟偑徯夘偝傟偰偄傑偟偨丅
丂俀寧偵擖偭偰丄乽徚旓巟弌俈擭楢懕尭彮丄嶐擭1.2亾尭丅僒儔儕乕儅儞悽懷怺崗丄IT娭楢偼戝暆憹乿偲丄怺崗側崙柉惗妶傪傛偦偵丄IT娭楢偼岲宨婥傪僀儊乕僕偡傞怴暦尒弌偟偑栚偵偲傑傝傑偟偨丅
丂乽憤柋挕偑俉寧敪昞偟偨1999擭偺壠寁挷嵏曬崘偵傛傞偲丄慡悽懷偺徚旓巟弌偼暔壙曄摦偺塭嬁傪彍偄偨幚幙偱1.2亾尭彮偟丄尰峴偺挷嵏傪巒傔偨1963擭埲棃弶偺俈擭楢懕儅僀僫僗傪婰榐偟偨丅宨婥偺掅柪偱強摼偑尭彮偟偨偙偲偑嬁偄偨丅徚旓慡懱偑怳傞傢側偄堦曽偱丄僷僜僐儞傗実懷揹榖側偳忣曬媄弍乮IT乯娭楢偺徚旓巟弌偼慜擭傪柤栚偱10.4亾忋夞傞崅偄怢傃傪帵偟偨丅IT娭楢偺徚旓偼惗嶻偺憹壛傪捠偠偰宨婥夞暅傪偗傫堷偡傞栶妱傕壥偨偟偰偄傞丅乮俀寧俋擔丒擔宱乯偲榑昡偟丄偙偙偱傕IT偑婄傪偩偟偰偄傑偟偨丅
丂挿堷偔晄嫷偑乽徚旓晄嫷乿偲偄傢傟偰偄傞傛偆偵丄崙柉惗妶慡懱偑椻偊偒偭偰偄傞偙偲偑惌晎偺摑寁帒椏偱傕柧妋偵側偭偰偄傑偡丅乽慡悽懷偺侾儠寧暯嬒偺徚旓巟弌偼侾悽懷偁偨傝32枩3008墌丅屬梡傗強摼偺埆壔傪攚宨偵丄怘旓傗堖椏昳側偳惗妶昁廀昳傊偺巟弌傪愡栺偡傞孹岦偑嫮傑偭偨丅怑嬈暿偵尒傞偲丄宨婥掅柪偺塭嬁傪嵟傕怺崗偵庴偗偨偺偼僒儔儕乕儅儞悽懷丅幚廂擖丄壜張暘強摼偲傕偵2.0亾尭偲挷嵏奐巒埲棃嵟戝偺尭彮暆偲側傞側偳廂擖柺偺棊偪崬傒偑傂傃偒丄幚幙徚旓巟弌偼慜擭斾偱1.7亾尭彮偟偨丅昳栚暿偱偼怘旓丄旐暈偍傛傃棜暔偑偲傕偵俋擭楢懕偱尭彮偟偨丅嫵堢旓傕夁嫀嵟戝偺尭彮暆偲側傝丄惗妶偵枾拝偟偨巟弌傪愗傝偮傔傞孹岦偑嫮傑偭偨丅
丂偙偆偟偨側偐偱IT娭楢偺徚旓巟弌偼僷僜僐儞丒儚乕僾儘偺傎偐丄実懷揹榖婡丒僼傽僋僗側偳偺捠怣婡婍偑戝暆側怢傃傪婰榐偟偨丅僀儞僞乕僱僢僩側偳僨乕僞捠怣偺憹壛傗実懷揹榖偺晛媦傪斀塮偟偰丄揹榖捠怣椏傕俆擭楢懕僾儔僗丅塹惎曻憲丒働乕僽儖僥儗價側偳曻憲庴怣椏傕憹偊偨丅IT娭楢巟弌傪崌寁偡傞偲擭娫偱12枩8741墌偲側傝丄僶僽儖宱嵪偑捀揰偵払偟偨89擭偺1.6攞偺嬥妟偵払偟偨丅乮恾乯
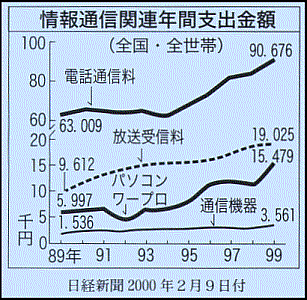
丂惗妶偺婎杮偲側傞堖丒怘丒廧傊偺巟弌偑愗傝偮傔傜傟丄IT娭楢傊偺徚旓偵傑傢偝傟偰偄偔偲偄偆崙柉惗妶偺幚懺偼丄壗傪堄枴偡傞偺偱偟傚偆偐丅IT妚柦偺婎斦偲側傞揹婥捠怣帠嬈偱偼偨傜偔巹偨偪偵偲偭偰丄IT娭楢偺徚旓偺怢傃偼巇帠偑傜婌傇傋偒偙偲側偺偱偟傚偆偐丄偳偆傕妱傝愗傟側偔丄媡偵怱偑偄偨傓婥偑偟傑偡丅
丂崙柉丒楯摥幰偑偍偐傟偰偄傞忬嫷偼丄愒怣崋偑偲傕偭偰偄傑偡丅惌晎偺屻墴偟偱嫮峴偟偰偄傞戝婇嬈偺儕僗僩儔乽崌棟壔乿傗憤恖審旓嶍尭偑丄崙柉惗妶慡懱傪榗傔偰偒偰偄傞偙偲傪偟傔偡傕偺偱丄偙偺備偑傒偑崙柉丒楯摥幰偺怱恎偵偳傫側塭嬁傪傕偨傜偡偐丅
丂嶐崱偺幮夛揑忬嫷傪尒傟偽丄帺嶦偺憹壛丄妛媺曵夡傗惵彮擭偺斊嵾側偳傪桿敪偝偣傞偽偐傝偐丄僀僨僆儘僊乕揑偵傕檵撨庡媊揑側僄儘僌儘丒僫儞僙儞僗偺暥壔忬嫷偵攺幵傪偐偗偰偄傞偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅
IT妚柦偺杮幙
丂儅僗僐儈巻忋傪偵偓傢偟偰偄傞乽IT妚柦乿偺妶帤偑偍偳傞巻柺偼丄壢妛媄弍偱偼側偔偰乽嶻嬈丒宱嵪乿巻柺丅摿偵丄姅幃傗搳婡娭楢偺婰帠丄宨婥偺摦岦偵偐偐傢傞曬摴偱偼昁偢偲偄偭偰偄偄傎偳乽IT乿偺暥帤偑偁傝傑偡偑丄偙偙偵IT妚柦偺杮幙偑尒偊塀傟偟偰偄傞傛偆偱偡丅
丂嫽枴傪堷偄偨偺偼丄IT妚柦偺杮幙偼忣曬庢堷偒僐僗僩偺寑揑側掅尭偱偁傞丄偲偟偰榑傪揥奐偡傞乽IT妚柦偺杮幙乿偑嵹偭偨俀寧俋擔偺擔杮宱嵪怴暦僐儔儉乽戝婡彫婡乿偱偟偨丅昅幰偼乽墶晽乿偲僱乕儈儞僌偑偁傞偩偗偱晄柧偱偡偑丄IT妚柦傪峫偊傞偆偊偱戝偒側庤偑偐傝偲側傝傑偟偨丅
丂乽墶晽乿巵偼丄IT妚柦偱偺曄壔偼乽忣曬媄弍嵿巗応偺旘桇揑惉挿乿偲乽忣曬媄弍棙梡巗応偺寑揑側曄壔乿偩偲偟偰偄傑偡丅
丂乽忣曬媄弍嵿巗応偱偼師乆偲怴惢昳偑惗傑傟丄廀梫傪桿偆丅惗嶻偼憹偊丄宱嵪惉挿傪墴偟忋偘傞丅懡偔偺媄弍偼僱僢僩儚乕僋宆丅忣曬偺揱払曽幃偼憃曽岦丅庤巻傗揹榖側偳偺屆揟揑捠怣偼丄屄偲屄偺娫偺憃曽岦揱払媄弍偩偭偨丅曻憲偼屄偐傜懡悢傊偺堦曽捠峴偩丅IT妚柦偼懡悢偲懡悢偺憃曽岦媄弍丅捠怣偲曻憲偺梈崌偼摉慠偺婣寢偲偄偊傞丅
丂忣曬媄弍棙梡巗応偵傕寖偟偄曄妚傪敆傞丅忣曬庢堷偒僐僗僩偺寑揑側掅壓偲偼姰慡巗応壔偺偙偲丅嬒峵揰払惉偑懍傑傝丄帒尮攝暘偼揔惈偵側傞丅偮傑傝彜択偼師乆偵傑偲傑傞丅倕價僕僱僗偵孮偑傞備偊傫偩丅恖乆偺岠梡偼崅傑傝丄廀梫偼憹偊惗嶻憹偵寢傃偮偔丅宱嵪惉挿偼偙偺柺偐傜傕墴偟忋偘傜傟傞丅忣曬偺旕懳張惈偵埶嫆偟偰偄偨娫愙嬥梈傗姱椈慻怐偼弅彫傪敆傜傟傞丅婇嬈丄壠懓丄崙壠側偳偺慻怐偵傕尒捈偟傪敆傞丅慻怐慻惉偺摦婡偼堄幆丒柍堄幆傪栤傢偢丄偁傞栚揑払惉偺偨傔偵僐僗僩傪嵟彫偵偡傞偩偙偲偩丅乿
丂乽墶晽乿巵偺乽IT妚柦乿榑偼丄僀儞僞乕僱僢僩傗実懷揹榖丄俤儊乕儖偺尵梩偙偦弌偰偒傑偣傫偑丄揹婥捠怣栐偺僨僕僞儖壔傪傆傑偊偨忣曬捠怣婎斦偺寖曄偵偲傕側偄丄崙柉惗妶傪傆偔傔偨幮夛妶摦偵戝偒側曄壔偑桿敪偝傟傞偙偲傪僐儞僷僋僩偵偺傋偰偄傑偡丅尷傜傟偨帤悢偺偣偄傕偁偭偰丄榑棟偺旘桇偑偁傝棟夝偟偯傜偄柺偑偁傝傑偟偨偑丄偲偵傕偐偔偵傕乽墶晽榑乿傪嶲峫偵IT妚柦榑傪偝偖傝傑偟偨丅
丂偦偆偙偆偟偰偄傞偆偪偵係寧枛丄擔杮宱嵪傕傛偆傗偔怴偟偄敪揥抜奒偺懅悂偒偑姶偠傜傟傞傛偆偵側偭偰偒偨丅忣曬媄弍乮IT乯偑偦偺尨摦椡偱偁傞丄偲偟偨乽IT妚柦偺杮幙乿偑丄崱搙偼擔宱怴暦偺乽廫帤楬乿偲偄偆僐儔儉偵搊応偟傑偟偨丅彁柤擖傝偱宱嵪嶻嬈傪尋媶偡傞夛幮戙昞偺媑揷弔庽偝傫偲偄偆曽偑堄尒傪偺傋偰偍傜傟傑偟偨丅
丂乽IT妚柦偼丄戞俀偺嶻嬈妚柦偲偄傢傟傞丅18悽婭偺嶻嬈妚柦偵傛傝恖椶弶傔偰僄僱儖僊乕傪摦椡偲偟偰梡偵偄傞傛偆偵側傝丄岺嬈幮夛偑抋惗偟偨丅IT妚柦偼丄偦偺岺嬈幮夛傪忣曬幮夛丄抦揑幮夛偲傛偽傟傞億僗僩岺嬈幮夛傊岦偗偰敪揥偝傟傞傕偺側偺偩丅
丂岺嬈幮夛偵偁偭偰偼丄儌僲偑晅壛壙抣偑惗傒弌偡宱嵪幮夛偱偁傞丅億僗僩岺嬈幮夛偼丄忣曬偑晅壛壙抣傪惗傒弌偡丅僐儞僺儏乕僞偲僱僢僩儚乕僋偺敪払偼棳捠嬈偵怴偟偄巗応傪採嫙偟嬥梈嬈偺嵼傝曽傪堦曄偝傟傞椡傪帩偮丅惢憿嬈傕丄傕偆堦抜偺柍恖壔偑恑傓丅IT妚柦偺杮幙偼丄偦傟偑捠怣偺敪払傪壛懍偡傞偺偵壛偊丄怴偟偄忣曬嶻嬈傪憂憿偡傞偲偙傠偵偁傞丅栤傢傟傞偺偼丄偦偺僐儞僥儞僣乮忣曬偺撪梕乯偱偁傞丅乿
IT妚柦偱丄婇嬈塰偊偰丄柉朣傇偺偐
丂崙柉丒楯摥幰偺惗妶埆壔傪傛偦偵丄乽忋応婇嬈丄俁擭傇傝10.7亾憹塿丅IT搳帒婑梌丄棃婜傕憹塿傊乿偲偺尒弌偟偑俁寧係擔偺擔宱怴暦偺僩僢僾傪偐偞傝傑偟偨丅
丂乽擔杮宱嵪怴暦幮偑俁擔丄忋応婇嬈偺2000擭俁寧婜偺嬈愌梊憐傪廤寁偟偨偲偙傠丄婜娫偺傕偆偗傪帵偡宱忢棙塿偼慜婜斾10.7亾憹偊傞尒捠偟偲側偭偨丅墌崅傗惢昳壙奿偺壓棊側偳偱攧忋偘偺尭彮偼懕偔偑丄儕僗僩儔僋僠儍儕儞僌乮帠嬈偺嵞峔抸乯偵傛傞僐僗僩嶍尭偺傎偐丄忣曬媄弍乮IT乯搳帒偺奼戝傗傾僕傾巗応偺暅挷側偳偑僾儔僗偵摥偒丄俁擭傇傝偵憹塿偲側傞丅徚旓偺掅柪偑懌偐偣偵側偭偰偄傞傕偺偺丄IT搳帒偺惙傝忋偑傝側偳偱2001擭俁寧婜傕憹塿偵側傞尒捠偟偩丅乿偲丄挿婜晄嫷側偵偡傞傕偺偧偲嫮婥偺榑昡偑偁傝傑偟偨丅
丂宱忢棙塿偺夞暅傪偗傫堷偡傞偺偼敿摫懱惢昳丄揹巕晹昳側偳IT搳帒偺壎宐傪偆偗傞婇嬈孮丅墌崅傗壙奿壓棊偱丄慡懱偱偼俁婜楢懕偺攧忋尭傪嫮偄傜傟傞偑丄恖堳嶍尭丄媼梌懱宯偺尒捈偟側偳偺岠壥偱彜幮丄奀塣側偳10嬈庬偑尭廂偱傕憹塿偲側傞丄偲夝愢偵偁傞偲偍傝丄嵿奅丒戝婇嬈偼儕僗僩儔偲IT妚柦傪僉乕儚乕僪偵丄晄嫷偱傕楯摥幰傊偺媇惖揮壟偱偒傝偸偗丄攧忋偘偑尭偭偰傕乽傕偆偗乿偩偗偼偟偭偐傝偲妋曐偡傞宱塩愴棯傪妋棫偟偰偒偰偄傞傛偆偱偡丅
丂夛幮偺栚揑偼栕偗傞偙偲偵偁傝傑偡偑丄儌僲傪偮偔偭偰傕丄攧傟側偄忬嫷偱偳偆偟偰傕偆偗傪偮偔傝偩偡偙偲偑偱偒傞偺偐丄怴偨側媈栤偑傢偄偰偒傑偟偨丅
丂擔杮偺婇嬈偑乽尭廂憹塿乿偺宱塩愴棯傪妋棫偟偼偠傔偨偺偼宱嵪僒儈僢僩偱乽僾儔僓崌堄乿偑嵦戰偝傟偨1985擭崰偱偼側偐偭偨偐偲巚偄傑偡丅憃巕偺愒帤嵿惌偵擸傓傾儊儕僇惌晎偲嵿奅偑擔杮偺敎戝側杅堈崟帤傪偼偒偩偝偣傞偨傔偵栆慠側擔杮偨偨偒偑偼偠傑偭偨偺傪巚偄偩偟傑偡丅
丂擔杮偺桝弌娭楢婇嬈傪拞怱偵丄媫寖側墌崅偵懳墳偡傞偨傔偵儕僗僩儔乽崌棟壔乿偑偡偡傓堦曽丄孯奼丒椪挷楬慄偵傕偲偯偄偰偙傟傑偱擔杮偺嶻嬈傪儕乕僪偟偰偒偨揝丒帺摦幵丒揹婡偵偐傢偭偰忣曬娭楢嶻嬈偺戜摢偑偼偠傑傝偟傑偟偨丅僶僽儖宱嵪偺崅梘偲曵夡傪宱夁偡傞側偐偱丄忣曬捠怣娭楢傊偲愝旛搳帒偺棳傟偑曄傢傞偩偗偱側偔丄婇嬈懱幙偺夵妚傕偼偠傑傝傑偟偨丅
丂揹婥捠怣暘栰偱傕丄捠怣栐偺僨僕僞儖壔偑偡偡傒僐儞僺儏乕僞偲恖丄僐儞僺儏乕僞偳偍偟偺捠怣偑壜擻偵側傝丄僯儏乕儊僨傿傾偐傜儅儖僠儊僨傿傾傊偲曄杄偑偼偠傑傝傑偟偨丅崙柉偺嫟桳嵿嶻偱偁偭偨揹揹岞幮偑85擭偵柉塩壔偝傟NTT偑抋惗丅嶐擭偮偄偵愴屻弶偺弮悎帩偪姅夛幮偺傕偲偵暘妱乽嵞曇惉乿偝傟丄姰慡柉塩壔偵傓偗偨摦偒偑嫮傑偭偰偄傑偡丅捠怣偺岞嫟惈偑曻婞偝傟丄儕僗僩儔乽崌棟壔乿偲崙柉丒棙梡幰傊偺僒乕價僗掅壓偑寽擮偝傟偰偄傞偲偙傠偱偡丅
丂偄偆傑偱傕側偔丄揹婥捠怣帠嬈偼揹椡偲偲傕偵乽IT妚柦乿傪巟偊傞婎斦偲偟偰側偔偰偼側傜側偄嶻嬈偱丄偟偐傕昁偢傕偆偐傞嶻嬈偲偟偰拲栚傪偁偮傔偰偒偨偐傜偙偦寖楏側嫞憟偲嶲擖偑偼偠傑偭偰偄傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅
IT妚柦偼丄擔杮偱惉岟偡傞偐
丂乽暷宨婥丄惗嶻惈岦忋偑庡摫丅GDP怢傃偺婑梌丄IT娭楢俀乣俁妱乿丄偲偄偆尒弌偟偵偮偯偔儚僔儞僩儞偐傜偺摿攈堳曬摴偱偼乽僋儕儞僩儞暷戝摑椞偼俀寧10擔丄2000擭戝摑椞宱嵪曬崘傪媍夛偵採弌丅俀寧偱夁嫀嵟挿偵側偭偨暷宨婥奼戝偵偮偄偰忣曬媄弍乮IT乯妚柦偑戝偒偔婑梌偟偨偲暘愅丄95擭偐傜係擭娫偺崙撪憤惗嶻乮GDP乯偺怢傃偺俀乣俁妱偑IT娭楢偲偺帋嶼傪柧傜偐偵偟偨丅IT妚柦傪攚宨偵婇嬈偺惗嶻惈偑岦忋偟偰偄傞偆偊丄亀嵿惌愒帤嶍尭偑柉娫搳帒偺奼戝梋抧傪傕偨傜偟偨亁偲傕巜揈丄暷宱嵪偺愭峴偒偵帺怣傪帵偟偨丅乿偲揱偊偰偄傑偡丅
丂傾儊儕僇惌晎偼97擭偵僀儞僞乕僱僢僩揹巕彜庢堷偺悇恑嶔傪敪昞偟丄惂搙柺偐傜怴媄弍偺妶梡傪屻墴偟偟偰偒傑偟偨丅暷彜柋徣偵俀擭慜偺98擭乽僄儅乕僕儞僌丒僨僕僞儖僄僐僲儈乕乮僨僕僞儖宱嵪偺戜摢乯乿偲偄偆曬崘彂傪敪昞丄90擭戙敿偽偐傜偮偯偔傾儊儕僇偺岲宨婥偼丄乽IT妚柦乿傪18悽婭偺嶻嬈妚柦偵側偧傜偊丄偦傟偑暷崙偺宱塩惉挿偵戝偒偔婑梌偟偰偄傞偲儗億乕僩偟偰偄傑偡丅
丂乽擔杮偱傕怴偟偄忣曬媄弍乮IT乯傪巊偭偨宱嵪夵妚丄偡側傢偪亀IT妚柦亁偑巒傑偭偨丅怷婌楴庱憡偼強怣昞柧墘愢偱亀IT妚柦亁傪婲敋嵻偲偟偨宱嵪敪揥傪偲慽偊丄俈寧偺庡梫崙庱擼夛媍乮壂撽僒儈僢僩乯偱傕IT偑偼偠傔偰庡梫壽戣偵忋傞丅
丂亀IT亁偼偐偭偰偺亀儅儖僠儊僨傿傾亁偲摨條丄條乆側掕媊偱岅傜傟傞丅僐儞僺儏乕僞傗捠怣媄弍傪巜偡側傜愴慜偐傜懚嵼偟偨丅偄傑夵傔偰亀IT亁偲嫮挷偝傟傞偺偼丄媫懍側惃偄偱悽奅偵峀傑偭偨僀儞僞乕僱僢僩偑丄忣曬偺棳傟傗儌僲偺摦偒傪戝偒偔曄偊傛偆偲偟偰偄傞偐傜偩丅乿乮俆寧俆擔丒擔宱乯偲丄僀儞僞乕僱僢僩偼擔杮嵞惗偺婲敋嵻偩偲偟偰丄怴暦偺乽幮愢乿偵傑偱搊応偡傞傛偆偵側傝傑偟偨丅
丂俁寧偼偠傔丄偁傞戝庤彜幮偺幮挿岎戙偺恖帠偺撪掕偑曬摴偝傟傑偟偨丅乽摨幮偼幮挿岎戙傪婡偵丄忣曬媄弍乮IT乯娭楢帠嬈傪拰偲偟偨惉挿愴棯傪壛懍偡傞丅憤崌彜幮偺棙塿偺尮愹偩偭偨慺嵽傗怘椏丄婡夿側偳庢堷拠夘偺岥慘價僕僱僗偼愭嵶傝偑妋幚丅懠幮傕摨條偺愴棯傪懪偪弌偟偰偍傝丄崱屻偼IT娭楢帠嬈偑彜幮偺庡愴応偵側傞乿偲偟偰丄FT乮嬥梈媄弍乯偲LT乮暔棳媄弍乯偵IT傪慻傒崌傢偣丄庢堷愭婇嬈偵條乆側僒乕價僗傪採嫙偡傞怴偨側彜幮婡擻傪慡柺偵懪偪弌偟偰偄偔峫偊偑徯夘偝傟偰偄傑偟偨丅
丂乽儔乕儊儞偐傜儈僒僀儖傑偱乿偲偄傢傟傞戝庤憤崌彜幮偼擔杮宱嵪偺弅恾偺傛偆側偺偱丄儌僲偺攧攦傪傗傔偰壗偱傕偆偗偰偄偔偺偐丄崱屻偺摦岦偑婥偵側傝傑偡丅
丂儅僗僐儈偱戝庤彜幮偺夛幮夵妚偑偼側偽側偟偔徯夘偝傟傞堦曽偱丄崙嵺揑側夛幮奿晅偗偑俀儔儞僋壓偑傝丄嬧峴偐傜崅偄嬥棙傪敆傜傟偰偄傞偲偟偰丄楯摥幰偵偼戝婯柾儕僗僩儔乽崌棟壔乿峌寕偑偐偗傜傟偰偒偰偄傑偡丅俇恖偺侾恖傪戅怑偝偣傞偲偄偆恖堳嶍尭丅崙嵺夛寁婎弨摫擖傪傂偐偊700幮偁傞巕夛幮偺偆偪丄傕偆偐傜側偄愒帤偺200幮偺惍棟丒搼懣丅偦偟偰憤恖審旓嶍尭傪偹傜偭偰怴恖帠惂搙偺摫擖側偳偱偡丅偄偔傜乽楢崌乿楯慻偑恖傋傜偟乽崌棟壔乿偲偨偨偐傢側偄偲偟偰傕丄屬梡傗捓嬥偼楯摥幰偵偲偭偰偼巰妶栤戣丄偙傟傑偱夛幮偵拤惤傪惥偭偰偄偨傛偆側楯摥幰傕曄傢傝偼偠傔丄怑応偐傜斀寕偑偼偠傑偭偰偄傑偡丅
丂捠嶻徣偼嶐擭俋寧丄乽IT妚柦偑傕偨傜偡屬梡峔憿偺曄壔乿偲戣偡傞挷嵏曬崘傪敪昞偟乽IT妚柦偱屬梡憂弌傊偺婑梌偑婜懸偝傟偰偄傞乿偲儉僱傪偼偭偰偄傑偡丅崱屻俆擭娫偵354枩恖偺屬梡偑嶍尭偝傟傞堦曽丄怴偨偵367枩恖偺屬梡偑憂弌偝傟丄嵎偟堷偒13枩恖偺弮憹偵側傞偲悇寁偟偰偄傑偡偑丄嶍尭偝傟偨楯摥幰偑嵞屬梡偝傟傞偲偼尷傜偢丄傛傝埆偄楯摥忦審偑懸偪偆偗傞偲偄偆僀儞僠僉側傕偺偱偡丅
丂偙偺俁寧偵梄惌徣偑乽IT妚柦乿偺岠梡傪愢偄偨揹婥捠怣怰媍夛偺摎怽乽21悽婭偺忣曬捠怣價僕儑儞乮IT JAPAN for ALL乯乿傪敪昞丄暥柧偺戝偒側揮姺揰偵棫偮擔杮偵偁偭偰丄墴偟婑偣傞IT乮忣曬捠怣媄弍乯偵傛傞曄妚偺攇偵忔傝偍偔傟傞側偲烔傪偲偽偟偰偄傑偡丅
丂乽IT偑扴偆忣曬嶻嬈妚柦偼扨側傞堦夁惈偺僩儗儞僪偱偼側偔丄21悽婭傪偮傜偸偔戝挭棳偲偄偊傞丅偐偮偰偺忲婥婡娭偺敪柧偑嶻嬈妚柦偺婲敋嵻偲側傝丄侾師嶻嬈乮擾嬈乯偐傜俀師嶻嬈乮惢憿嬈乯傊偺堏峴傪偆側偑偟偨傛偆偵丄IT偼偄傑戞俀偺嶻嬈妚柦傪堷偒婲偙偟丄戞俁師嶻嬈乮僒乕價僗嬈乯偐傜係師嶻嬈乮忣曬嶻嬈乯傊偺枊傪奐偙偆偲偟偰偄傞丅
丂忣曬嶻嬈偼丄僀儞僞乕僱僢僩媄弍傪拞怱偵丄儌僶僀儖婡婍丒僷僜僐儞側偳偺乽僴乕僪僂僄傾乿丄倕亅僐儅乕僗丒僨乕僞僒乕價僗側偳偺乽僜僼僩僂僄傾仌僒乕價僗乿丄敿摫懱丒CPU側偳偺乽揹巕丒揹婥婡婍乿僎乕儉丒僨僕僞儖曻憲丒壒妝側偳偺乽儊僨傿傾乿丄僱僢僩儚乕僋僀儞僼儔側偳偺乽捠怣乿丄偲偄偆偍偍傛偦俆偮偺暘栰偵峀偑偭偰偄傞丅偦傟傕丄奺暘栰偺媄弍偼憡屳偵梈崌偟丄傑偭偨偔怴偟偄巗応傪憂傝弌偟偮偮偁傞丅
丂IT偺恑揥偑嶻嬈妚柦偨傝偆傞偺偼丄IT偑傑偭偨偔怴偟偄僀儞僼儔偺採嫙傪傕偨傜偟丄婛懚偺偡傋偰偺嶻嬈偺惗嶻惈傪旘桇揑偵崅傑傞偐傜偵傎偐側傜側偄丅偦偺堄枴偱忣曬嶻嬈妚柦偼偙傟偐傜偑杮斣丅偄傑傑偝偵巒傑偭偨偽偐傝偲偄偊傞丅乿
丂偙傟偼丄偁傞搳帒夛幮偑IT娭楢柫暱傪偡偡傔傞怴暦峀崘偺僐僺乕偱偡偑丄乽IT妚柦乿偱忋庤偵帒嶻塣梡傪偲傾僺乕儖偟偰偄傑偡丅偄傑IT娭楢偺儀儞僠儍乕婇嬈偺愝棫偑偁偄偮偄偱偄傑偡偑丄惌晎偼儀儞僠儍乕婇嬈堢惉偺偨傔偵尰峴彜朄偺婯惂傪娚榓偡傞朄惍旛偺専摙偵偺傝偩偟偰偄傑偡丅
丂儀儞僠儍乕丒僉儍僺僞儖乮儀儞僠儍乕婇嬈偵偨偄偡傞搳帒夛幮乯偼丄弌帒偟偨婇嬈偺姅幃忋応偵傛傞姅壙崅摣偱摼傞僉儍僺僞儖丒僎僀儞乮姅幃攧攦嵎塿乯傪偹傜偄丄儌僲偯偔傝偺宱嵪偐傜搳婡宱嵪傊偲攺幵傪偐偗偰偄傑偡丅
怴媄弍傪暯榓偲朙偐側崙柉惗妶偺偨傔偵
丂IT妚柦偲偼側偵偐丠楯摥幰偲崙柉偵壗傪傕偨傜偡偺偐丄偲偄偆柦戣偺夝柧偵偼傕偆彮偟帪娫偑偐傞傛偆偱偡偑丄岝偲塭偺椫妔偑偟偩偄偵偼偭偒傝偟偰偒偨傛偆偵巚偄傑偡丅
丂NTT宯偺僔儞僋僞儞僋偱偁傞忣曬捠怣憤崌尋媶強偼丄嘆2003擭偵偼擔杮偺悽懷偺60亾埲忋丄墑傋恖岥偱侾壄恖埲忋偑僀儞僞乕僱僢僩傪棙梡偡傞丅嘇暷崙偲偺斾妑偱偼丄屌掕栐偵傛傞僀儞僞乕僱僢僩偺悽懷晛媦棪偼傎傏尐傪側傜傋丄屌掕栐偲実懷揹榖傪崌傢偣偨僀儞僞乕僱僢僩偺恖岥晛媦棪偱偼丄2001擭偵傕暷崙傪捛偄墇偡偺偱偼偲偄偆梊應寢壥傪敪昞偟傑偟偨丅
丂擔杮偱偺僀儞僞乕僱僢僩偺98擭偺悽懷晛媦棪偼11亾丅99擭偼20亾偵払偟偨偲悇寁偝傟偰偄傑偡偑丄堦斒揑偵偼悽懷晛媦棪偑侾妱傪偙偊傞偲幮夛傊偺怹摟偑憗偄偲偄傢傟偰偄傑偡丅揹榖偺応崌悽懷晛媦棪侾妱傪偙偊傞偺偵76擭丄実懷揹榖偼15擭娫偐偐傝傑偟偨偑丄僀儞僞乕僱僢僩偼俇擭丅偄偐偵嬃堎揑側僗僺乕僪偱晛媦偟偰偄傞偐偑傢偐傝傑偡丅
丂傾儊儕僇崙杊憤徣偱孯帠栚揑偵奐敪偝傟偨僀儞僞乕僱僢僩偑丄90擭偵暷崙偱丄93擭偵擔杮偱愙懕壜擻偵側傝丄崙嫬傪墇偊丄帪嵎傪偙偊偰慡悽奅偲弖帪偵傾僋僙僗偑壜擻偵側偭偨偄傑丄乽IT乿傪嵿奅丄戝婇嬈偑撈傝偠傔偟丄傕偆偗傗儕僗僩儔乽崌棟壔乿偺摴嬶偵偡傞偺偱偼側偔丄偳偆暯榓偲朙偐側崙柉惗妶偵栶棫偰傞偐偑栤傢傟偰偄傑偡丅
乮偲偪偍丒偠傘傫丒捠怣楯慻暃埾堳挿乯
嵟嬤姶偢傞偙偲
捤揷丂媊旻
仜丂抧堟偱桳巙偑偁偄廤偄慡楯楢壛柨偺擭嬥幰慻崌偺巟晹傪偮偔偭偰偐傜10擭偵側傝傑偡丅嫃廧抧偱慻怐傪偮偔傞偲偄偆枹奐戱偺暘栰傊偺偲傝偔傒偱偁傝丄寢廤偼梕堈偱偼偁傝傑偣傫丅庤扵傝偺塣摦偱偟偨丅摥偄偰偄偨帪偵懳墳偟偰丄岤惗擭嬥丄嫟嵪擭嬥丄崙柉擭嬥側偳偺堘偄傕偁傝丄擭嬥偺側偄恖傑偱偄傑偡丅傕偪傠傫丄崱栤戣偵側偭偰偄傞慻崌旓偺揤堷偒側偳偼偁傝偊偢丄侾恖侾恖偐傜偍偝傔偰偄偨偩偄偰偄傑偡丅婡娭巻丒僯儏乕僗丄楢棈側偳偺攝払傕戝愗偱偡丅偙偆偟偨攝払丒廤嬥偺巇帠偼10悢恖偺幏峴晹偺擟柋偺戝偒側斾廳傪偟傔偰偍傝丄傑偝偵曬廣側偒儃儔儞僨傿傾妶摦偺揟宆偱偡丅
丂偙偆偟偰俀偮偺帺帯懱偵傑偨偑傝30柤偱僗僞乕僩偟偨巟晹傕懡偔偺傒側偝傫偺偛嫤椡傪偊偰10擭偱傛偆傗偔120柤傪偙偊傞偵偄偨傝傑偟偨丅崅楊幰偺廤傑傝偱偡偐傜丄昦庛偺恖偑懡偔丄側偔側傞曽傕偄傞偟丄憹傗偝側偗傟偽尭傞偲偄偆摉偨傝慜偺偙偲傪壗偲偐忔傝墇偊偰偒偨偲偄偆姶偠偱偡丅俆廃擭偺帪偵偼婰擮帍傪偮偔傝傑偟偨偑丄偄傑10廃擭婰擮帍傪廐傑偱偵偮偔傞傋偔丄傒側偝傫偵尨峞埶棅拞偱偡丅嶐擭偺乽崙嵺崅楊幰擭乿偵傂偒偮偯偒丄崱擭乽崙嵺崅楊幰偺10擭乿偑崙楢憤夛偱嵦戰偝傟傞偙偲偵懳墳偟偰丄偦傟傜傪捠偠偰偙傟傑偱偺塣摦傪憤妵偟丄21悽婭偵傓偗偰偺崅楊幰塣摦偺慜恑偺椘偲偟偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅
仜丂搶嫗偱偼傎偲傫偳偺嬫巗偱幮夛曐忈悇恑嫤媍夛乮幮曐嫤乯偑妶摦偟偰偄傑偡偑丄崱擭侾寧戝曄抶傟偽偣側偑傜丄搚寶丄怴晈恖丄嫵慻丄暉巸曐堢楯側偳偲嫟摨偟偰抧堟偺幮曐嫤傪僗僞乕僩偝偣傑偟偨丅
丂係寧丄搶嫗幮夛曐忈妛峑偵偼偠傔偰嶲壛偟丄27夞偲偄偆楌巎偲揱摑偵嬃偒傪妎偊側偑傜偒偄偰偄偰丄島巘愭惗偺榖傕戝曄嶲峫偵側傝傑偟偨偑丄係寧偐傜巤峴偝傟偨夘岇曐尟偵偮偄偰偺尰応偐傜偺曬崘傕愗幚側忬嫷偲偟偰偆偗偲傔傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅抧堟偺幮曐嫤偺応偱傕丄乽懡朲偱惗偒偰偄傞偺偑晄巚媍側偔傜偄乿偲偄偆摿暿梴岇榁恖儂乕儉怑堳偺偍榖偵乽偳偆偵偐偟側偔偰偼乿偲徟傝偝偊傕姶偢傞偺偱偡丅
丂偝偰僛儞僛儞摨柨偼俀寧偵夘岇楯摥幰侾枩恖傪寢廤偟偰乽擔杮夘岇僋儔僼僩儐僯僆儞乮NCCU乯乿傪僗僞乕僩偝偣丄擭撪俆枩恖偵奼戝偡傞偲偟丄帺帯楯偼30枩恖偺慻怐壔傪傔偞偟偰偄傞偲揱偊傜傟偰偄傑偡丅慡峘榩偺婇嬈慻崌乬働傾僼僅乕儔儉乭偺愝棫丄揹婡楢崌偺夘岇巟墖僱僢僩儚乕僋愝棫側偳傕曬摴偝傟偰偄傑偡丅戝曄偍偙偑傑偟偄尵偄曽偱偡偑丄偳偺慻怐偱傕傛偄丄偡傋偰戝偄偵嫞憟偟側偑傜戝抇偵忔傝弌偟偰傎偟偄傕偺偱偡丅
乮夛堳丒搶嫗搒堫忛巗嵼廧乯
丂係寧偺尋媶妶摦
係寧侾擔 丂擔杮揑楯巊娭學尋媶僾儘僕僃僋僩亖僌儘乕僶儕僛乕僔儑儞壓偺擔杮揑楯巊娭學 丂丂俆擔 丂楯摥帪娫栤戣尋媶晹夛亖曬崘丒摙榑乛乽楯摥椡廀媼偺揥朷偲壽戣亅屬梡惌嶔尋媶夛曬崘偺偲傝傑偲傔偵偮偄偰乮楯摥徣99擭俆寧25擔敪昞乯乿媦傃乽摉尋媶晹夛偺21悽婭弶摢偺尋媶寁夋乿偺専摙 丂丂11擔 丂惵擭栤戣尋媶晹夛亖曬崘丒摙榑乛嶳揷徆峅挊乽僷儔僒僀僩丒僔儞僌儖偺帪戙乿乮拀杸彂朳乯偺崌昡 丂丂14擔 丂崙嵺楯摥尋媶晹夛亖曬崘丒摙榑乛乽儓乕儘僢僷偵偍偗傞M&A偺摦岦偵偮偄偰乿 丂丂15擔 丂惌帯宱嵪摦岦尋媶晹夛亖曬崘丒摙榑乽儓乕儘僢僷偵偍偗傞惌帯宱嵪摦岦偲楯摥塣摦乿媦傃乽摉尋媶晹夛偺21悽婭弶摢偺尋媶寁夋乿 丂丂22擔 丂幮夛曐忈尋媶晹夛亖尋媶惉壥偺弌斉嶌嬈偺嬶懱壔偺専摙 丂丂25擔 丂彈惈楯摥尋媶晹夛亖曬崘丒摙榑乛乽夛幮暘妱朄埬乿媦傃乽屬梡曐尟夵埆埬乿偵偮偄偰
婑憽丒擖庤恾彂帒椏僐乕僫乕
- 杒栰惓堦挊乽尋媶帒椏No.51乛嶰旽揹婡偺宱塩楬慄傪傔偖偭偰乿乮暫屔導楯摥塣摦憤崌尋媶強丒99擭10寧乯
- 戞係夞奀奜宱嵪帠忣妛弍挷嵏儕億乕僩乽儔僆僗乿乮暫屔導楯摥塣摦憤崌尋媶強丒2000擭俀寧乯
- 屗栘揷壝媣挊乽楯摥慻崌偺尨揰乿乮妛廗偺桭幮丒2000擭係寧乯
- 嶳揷徆峅挊乽僷儔僒僀僩丒僔儞僌儖偺帪戙乿乮拀杸彂朳丒99擭10寧乯
- 尨揷幚丒埨堜峆懃丒崟揷寭堦曇挊乽憄彂尰戙宱塩妛亅12乛怴擔杮揑宱塩偲楯柋娗棟乿乮儈僱儖償傽彂朳丒2000擭係寧乯
- 慡楯楢曇乽悽奅偺楯摥幰偺偨偨偐偄劅悽奅偺楯摥慻崌塣摦曬崘2000擭斉劅乿乮2000擭係寧乯
- 乽暯惉10擭搙乛惗妶曐忈偵娭偡傞挷嵏乿乮惗柦曐尟暥壔僙儞僞乕丒98擭12寧乯
- 拞墰楯摥埾堳夛帠柋嬊乽暯惉10擭捓嬥帠忣摍憤崌挷嵏劅捓嬥帠忣挷嵏劅乿乮99擭俁寧乯
- 偊傂傔嬑楯幰惗妶忣曬僙儞僞乕乽2000擭乛偊傂傔惗妶敀彂乿乮2000擭俀寧乯
- 偊傂傔嬑楯幰惗妶忣曬僙儞僞乕乽壠寁挷嵏曬崘No.4乛垽昋偺壠寁劅1999擭壠寁挷嵏曬崘彂劅乿乮2000擭俁寧乯
- 偊傂傔嬑楯幰惗妶忣曬僙儞僞乕乽挷嵏丒尋媶曬崘No.20乛垽昋偵偍偗傞嬑楯幰偺惗妶偲峴摦劅嬑楯幰惗妶丒暉巸幚懺挷嵏劅乿乮2000擭俁寧乯
- 搶嫗搒楯摥宱嵪嬊楯惌晹楯摥慻崌壽曇廤丒敪峴乽楯摥娐嫬偺曄壔偲懡條壔偡傞摥偒曽乿乮2000擭俁寧乯
- 搶嫗搒楯摥宱嵪嬊楯惌晹楯摥慻崌壽曇廤丒敪峴乽暯惉11擭搙彈惈楯摥僈僀僪僽僢僋夵掶斉乛摥偒側偑傜弌嶻丒堢帣劅擠怭丒弌嶻偵娭偡傞曐岇偲堢帣媥嬈劅乿乮2000擭俁寧乯
- 搶嫗搒楯摥宱嵪嬊楯惌晹楯摥慻崌壽曇廤丒敪峴乽攈尛楯摥Q&A乿乮2000擭俁寧乯
- 搶嫗搒楯摥宱嵪嬊楯惌晹楯摥慻崌壽曇廤丒敪峴乽僙僋僔儏傾儖丒僴儔僗儊儞僩憡択儅僯儏傾儖乿乮2000擭俁寧乯
- 搶嫗搒楯摥宱嵪嬊楯惌晹楯摥慻崌壽曇廤丒敪峴乽擭曨惂偵娭偡傞幚懺挷嵏乿乮2000擭俁寧乯
丂係寧偺帠柋嬊擔帍
係寧15擔 丂楯摥幰嫵堢嫤夛戞41夞憤夛傊儊僢僙乕僕
丂丂99擭搙戞俀夞婇夋埾堳夛丂丂22擔 丂乽楯摥憤尋僋僅乕僞儕乕乿曇廤夛媍 丂丂28擔 丂慡楯楢曇乽2000擭崙柉弔摤敀彂乿崌昡夛乮杚栰丄捯壀丄嬥揷丄塅榓愳乯